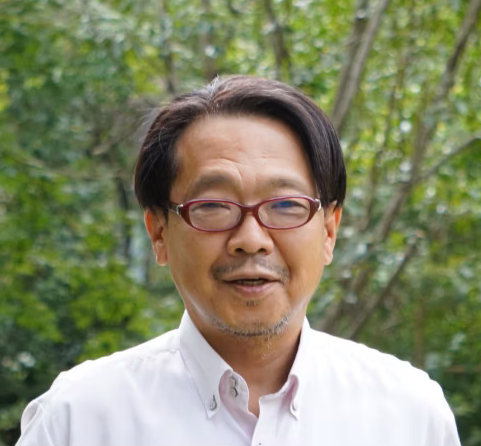
武蔵大学 経済学部 教授
2008/08 住友生命保険相互会社(退職)リスク管理統括部
1999/04 2001/03 九州大学経済学部 准教授 客員助教授(任期2年)
1990/04 (株)住友生命総合研究所(出向)
1987/04 住友生命保険相互会社(入社)佐賀支社
近年、ERM(統合リスク管理)の高度化が進んでいますが、日本の金融業界が今後取り入れるべき国際的なリスク管理手法や、その際に直面しやすい課題は何でしょうか。
リスクマネジメントにはハードとソフトがあります。従来は取締役会の積極的関与、リスク管理統括部の配置、リスクに関する報告体系と監査体制の確立、リスク管理方針の制定と手続きなど組織・規定等インフラ構築に重点が置かれてきました。これらハードの過度の強化は柔軟な意思決定の阻害要因となります。
現在はソフトにより重点があります。主な取り組みは、企業内のリスク・カルチャーの醸成、エマージング・リスクの把握、誠実な業務遂行、公正な業績評価システムの構築、報酬を含むインセンティブ体系の見直しなどです。ソフトは人、スキル、カルチャー、価値、インセンティブに焦点が当たります。
ソフトがリスク・テイクの促進要因となる一方、ハードは抑制要因です。リスクとリターンが表裏一体の関係にあってリスク調整済みリターンで意思決定を行うように、リスクマネジメントもハードとソフト双方のバランスをとる必要があります。ハードの解答は、他社の取組みや規制当局の指導を参考にして比較的容易に得られます。しかしソフトは企業ごとの個別性が強く、なかなか正解は見つかりません。
ERMの成功には、組織における学習がきわめて重要です。『愚者は経験に学び、賢者は歴史に学びます。』
金融機関のリスク管理において、現代の銀行や保険会社が直面する課題と、克服するために有効だと考えられる理論や実務的取り組みについて教えてください。
ERMの定量的手法はほぼ確立し、定性的な面がより重視されています。リーマンショックを契機にリスクアペタイト・フレームワークが導入されました。これは事業戦略・財務計画を達成するために、進んで引き受けるリスクの種類と量を明確化し、経営管理やリスク管理を行う枠組みです。
また経営陣は重大と思われるリスク(トップリスク)を特定化し、その対処法を予め定めておく必要があります。トップリスクは、経済環境、情報システム・テクノロジー、コンプライアンス、社会構造、自然災害など多岐にわたります。
解決策を導く理論=魔法の杖などなく、個別具体的に対応せざるを得ません。コンプライアンス、情報システム・テクノロジー関連であれば自らがコントルールできる範囲も大きく、リスクの発生予防に努めます。社会構造などは変化のトレンドが緩やかで予測可能な部分も多く、長期的視点にたって準備を粛々と進めます。
たとえば、店舗の統廃合や高齢者向けの商品開発などです。経済や自然災害は突発的にリスクが顕在化するため、対応の即応性が強く求められます。想定シナリオごとに個別対応策、コンティンジェンシープランを整備します。備えあれば憂いなしが要諦です。
「安心感」は経済活動に大きな影響を与えると言われます。先生のご研究の中で、安心感やリスク感情が消費や投資行動に及ぼす影響や、政策や企業の意思決定において考慮すべき点を教えてください。
売り手と買い手の間で「情報の非対称性」があるとき、市場が適切に機能しなくなります。たとえば、生命保険では保険会社がお客さんの健康情報がわからないとき、不健康な人しか保険に加入しない状況が生じます。市場競争に任せておけば価格が適正に決まるといった市場原理は、情報の非対称性のもとでは機能しません。
また情報の非対称性の存在は、モラルハザードを誘発します。1980年代、米国のS&Lの経営者は、預金者は経営状態を十分に理解できず(情報の非対称性)、かつ預金者は預金保険によって保護されている(=経営者が損失を弁償する必要がない)ことを背景に、商業不動産などのハイリスク資産に投資を行い破綻しました。
しかし石田梅岩は『都鄙問答』で、商人に倫理、正直な商売の必要性を説いています。経済活動が活発化していくうえでは、取引における相互の「信頼」が最も重要です。政治家や官僚が不正をしている国は経済成長率が低いことが明らかにされています。
取引相手や制度に不安を感じるような社会では取引が控えられ、経済の成長も鈍くなってしまう傾向にあります。そして相互の信頼を高めていくには、情報開示が十分に行われる必要があります。
保険業における規制緩和やグローバル化の進展を踏まえ、日本と諸外国の保険市場におけるリスク管理やガバナンスの違いについて、実証研究から明らかになった課題を教えてください。
2000年代以降の保険会社のソルベンシー(支払い能力)に関する国際的な潮流は、経済価値ベースの規制にあります。日本でも2026年3月末から適用されます。従来のソルベンシー規制が帳簿価額に基づいていたのに対し、資産と負債の公正価値評価を行います。公正価値は、資産・負債の将来キャッシュフローを経済実態にもとづく前提条件で割り引いて評価します。リスクバッファーとなる純資産額(資産額と負債額の差額)を経済価値ベースで算出し、将来生じうるリスクに対して充分であるかを検証します。
一方で経済価値ベースの評価は潜在的なリスクであって、まだ顕在化しているわけではないことに注意を払うべきです。純資産の公正価値の変動はデュレーション・ギャップに依存します。英米は変額年金・変額保険のような投資性商品や医療保険を中心として商品展開をしており、デュレーション・ギャップはさほど大きくなりません。
一方、日本の伝統的な生命保険会社は、定額・長期を特徴とする終身保険を販売していて、長期債を保有するとしてもデュレーション・ギャップを埋めるには限界があります。経済価値ベースのソルベンシー規制は、長期的トレンドを見ながら適切に評価すべきものです。
最後に、金融・リスクマネジメント分野を目指す学生や読者に向けて、研究や実務の両面で大事にすべき視点やスキルについてメッセージをお願いします。
金融・リスクマネジメントの分野を目指す方々がまず学ぶべきは、ファイナンス理論、統計学、計量経済学です。これらの科目はリスクマネジメントにおけるリスク計測及びモデルの理解に必須だからです。また、リスクマネジメントはハードからソフトへと重心が移っています。企業独自のカルチャー、報酬体系やインセンティブなどに配慮する必要性が高まっているため、経営学、とくに人事論や組織論に関する理解を深めておくことも肝要です。
しかし一方で、リスクマネジメントでは、理論よりも実務、実践がとても重要です。その際たる例は、ノーベル経済学賞を受賞したマイロン・ショールズなどが参加し、高度な金融工学理論を駆使したヘッジファンド、ロングタームキャピタルマネジメント(LTCM)の破綻です。
理論、モデルというのは仮定、前提条件に大きく依存していることを忘れてはいけません。トレンドをどのように読むかが勝敗の分かれ目です。リスクマネジメントはアート(芸術)だと言われる所以です。学問的知識だけでは十分ではなく、スキルがものをいいます。そのためには多くの実務経験を積んで、ベストプラクティスを身につけていく必要があります。

