
東京情報大学教授
横浜国立大学大学院工学研究科人工環境システム学専攻博士後期課程修了 博士(工学)。
2006年 (学校法人東京農業大学)東京情報大学総合情報学部総合情報学科 講師、2009年同准教授、2016同教授 現在に至る。
教育面では、プログラミング教育、シニアへのICT教育、留学生へのICT教育等にも注力しており、サイエンスライターとしても執筆活動および講演活動を行っている。
スクラッチプログラミングに関しては多数の論文や著書があり、スクラッチプログラミングに関する研究や著書の第一人者として著名である。
スクラッチプログラミングと通常のプログラミングの違いは、どういった点になりますか?
文字や数字をキーボードなどから入力して作成する通常のプログラミングを、コーディングプログラミングと言います。一方、スクラッチのようにブロックなどを並べて作成するプログラミングを、ビジュアルプログラミングと言います。
コーディングプログラミングは、ソフトウェア開発や科学技術計算を要する研究など幅広い用途で利用されていますが、修得するまでに時間がかかることや、文字や数字の打ち間違いなどのコーディングミスが必ずと言っていいほど起こります。
一方、スクラッチなどのビジュアルプログラミング言語はブロックを並べることが主な作業なので、入力ミスなどの心配はあまりありません。また、こどもでも扱うことができます。ただし、処理がブロックとしてまとまっているため、研究開発など専門的なことを行うのは不向きです。
教育的には、まずビジュアルプログラミングを学び、アルゴリズムなどを理解してから、通常のプログラミングであるコーディングプログラミングに移行するのがお勧めです。また、ビジュアルプログラミングはホビーとしても利用できますので、世代を超えて楽しめます。
スクラッチプログラミング言語を使用した教材の研究開発をしようと思ったきっかけと、目的を教えてください
2020年度から始まった小学校におけるプログラミング教育の必須化、さらに、その後段階的の行われた中学校、高等学校におけるプログラミング教育の充実に着目していました。なかでも、小学校におけるプログラミング教育の必須化は画期的な取り組みであり、世界的なIT技術の進展に対応した背景もあります。
大学生や大学院生にも言えることですが、全ての人がプログラミングに高い興味を持っているわけではありません。むしろ、多くの人は特に興味を持っていないと思います。こどもの場合、最初からプログラミングに興味を持っている割合は少ないと思いました。しかし、実際プログラミング教育が必須化され、今後も重要性が増して行くことはあきらかであるため、まずプログラミングに興味を持ってもらいたいと考えました。
そのため、興味深い教材の作成、書籍の執筆、さらには小中学校などの先生方へのスクラッチによる教材作成の研修などが必要であると考えました。今も小学校から大学・大学院までの教育現場にかかわり、研究・教育を深めています。
ChatGPTのような生成AIが普及する時代に、子どもたちがプログラミングを学ぶ意義はどう変化していくとお考えですか?
生成AIは急速に普及しつつあり、我々の日常生活に不可欠なものになると思います。すでに、ビジネスの現場ではかなり使われています。これらに制限をかける動きもありますが、過去の例から科学の進展は止めることができず、その利用範囲は広がっていくでしょう。
生成AIを使えばコーディングプログラムであればAIが生成してくれます。しかし、生成されたプログラムが正しいか、さらには効率的なものであるかなどを判断するには、しっかりとした知識が必要です。
したがって、生成AIが生成したものを判断したり、さらにはそれらを改良したりするためにもプログラミングを学習する意義は高いです。
プログラミングに興味を持ってもらうための取り組みとして、実際に行われたことを教えてください
スクラッチプログラミングに関しては、研究者および教育者の経験を生かした書籍作りからはじめました。2018年に教育的な流れや小学校の学習内容も考慮した『親子でかんたんスクラッチプログラミングの図鑑 / 技術評論社』を出版しました。共著者は一緒に著書の執筆や研究をしている、横浜国立大学の山本光教授です。
この本の後にもスクラッチプログラミング関連の本を出版し続けるとともに、小学生校でのスクラッチプログラミングに関する指導カリキュラムの作成、大学・大学院をも含めたスクラッチプログラミングに関する教育実践と教育効果の観察・分析をしてきました。教育実践にはこれらの著書も利用しています。
また、公開講座や市などの公的機関でのスクラッチプログラミングに関する講演も多数行ってきました。教育委員会主催のプログラミングに関する各種研修などでもスクラッチプログラミングに関するものを多数行ってきました。
最後にプログラミングに興味を持っている学生・社会人の方に向けてメッセージをいただけますでしょうか。
プログラミングは、教養や趣味として使う場合、さらにはIT技術者を目指して使う場合など、様々な場合があると思います。どのような目的で使う場合でも、プログラミングの学習においても最も大事なことは興味を持って行うことです。
私はプログラミングに対する興味喚起を目的として、スマホなどで撮影した素材や生成AIによる素材を利用した「コンテンツ利用プログラミング」(Wikipediaもご参照ください)に関する研究・教育を行っています。自分で取集した素材をプログラミングにより動かすことにより、オリジナルの作品を楽しく作成することができます。
みなさんもコンテンツ利用プログラミングやゲーム制作など、楽しみながらプログラミングに挑戦してみてください。
松下孝太郎教授の著書
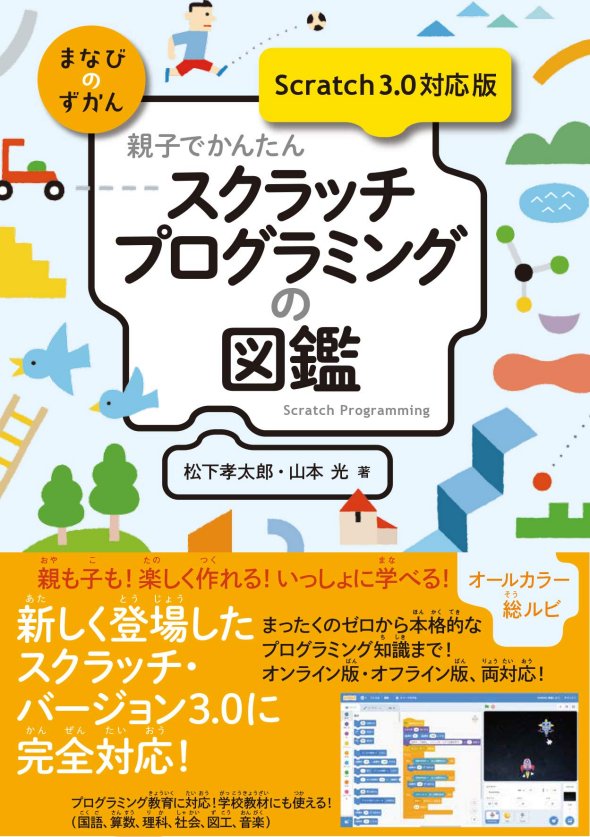

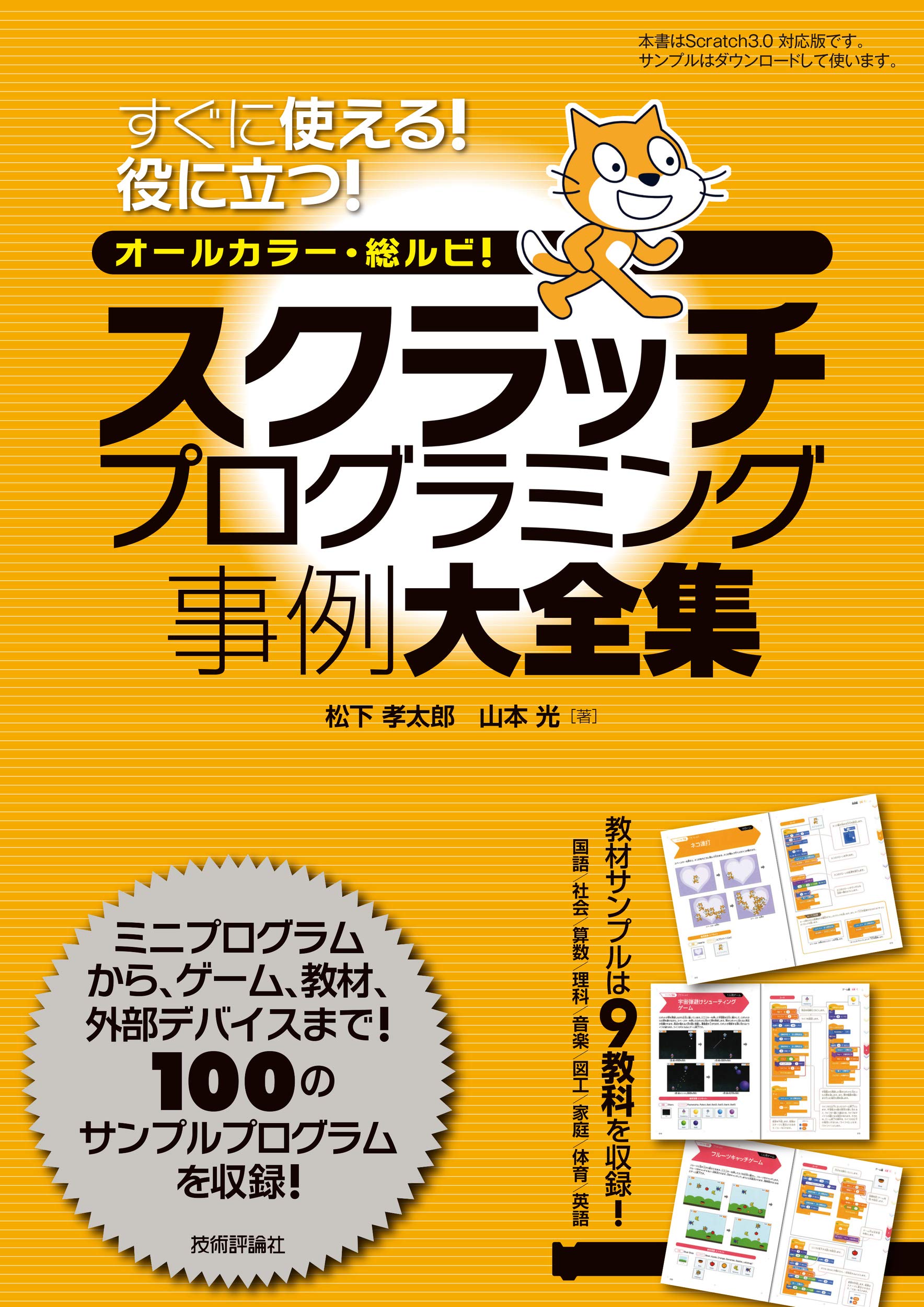
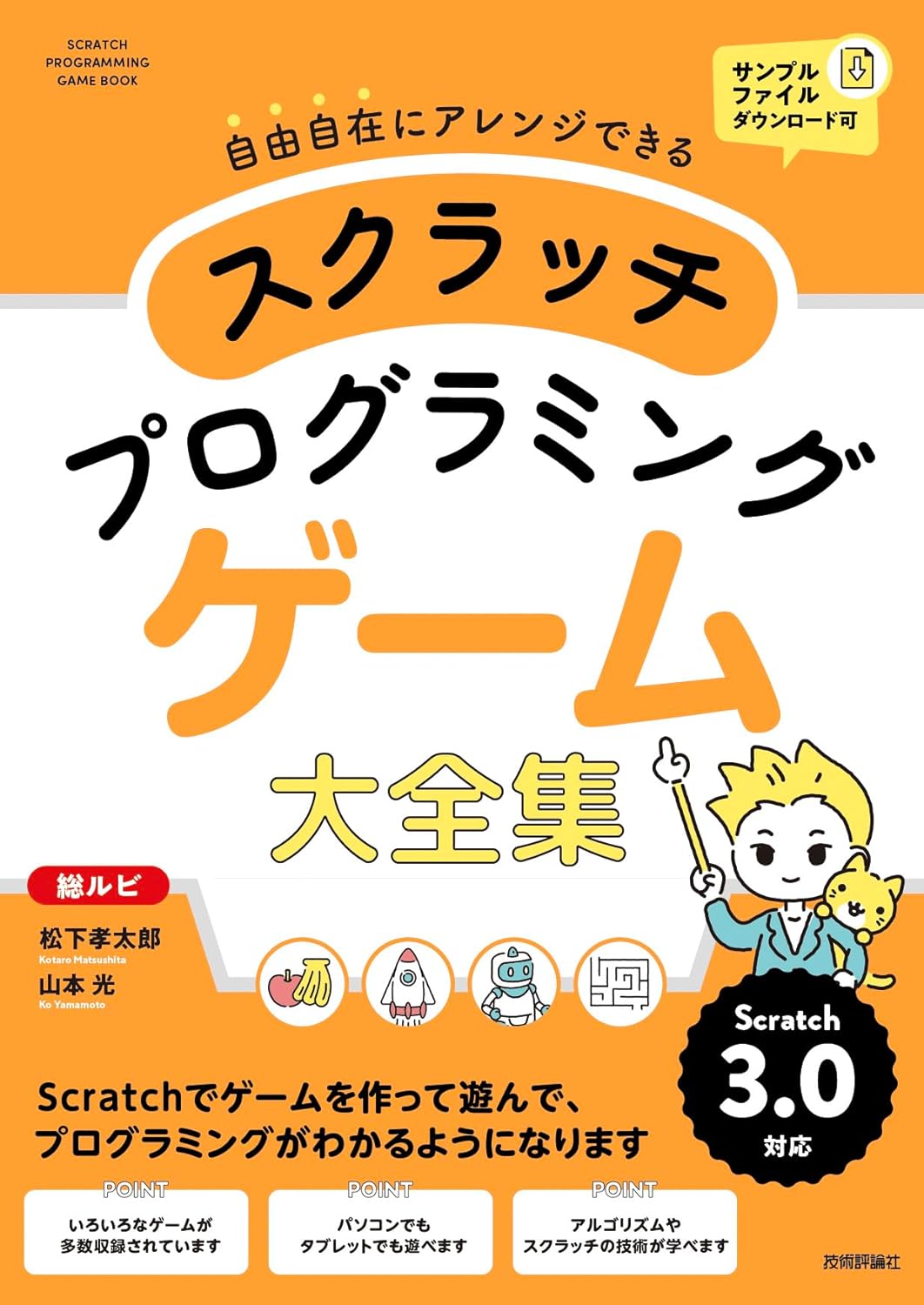
#松下孝太郎 #スクラッチプログラミング

