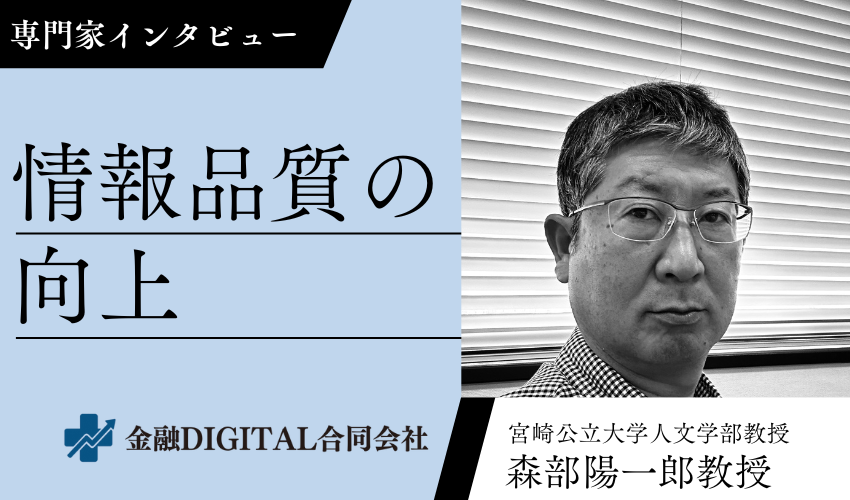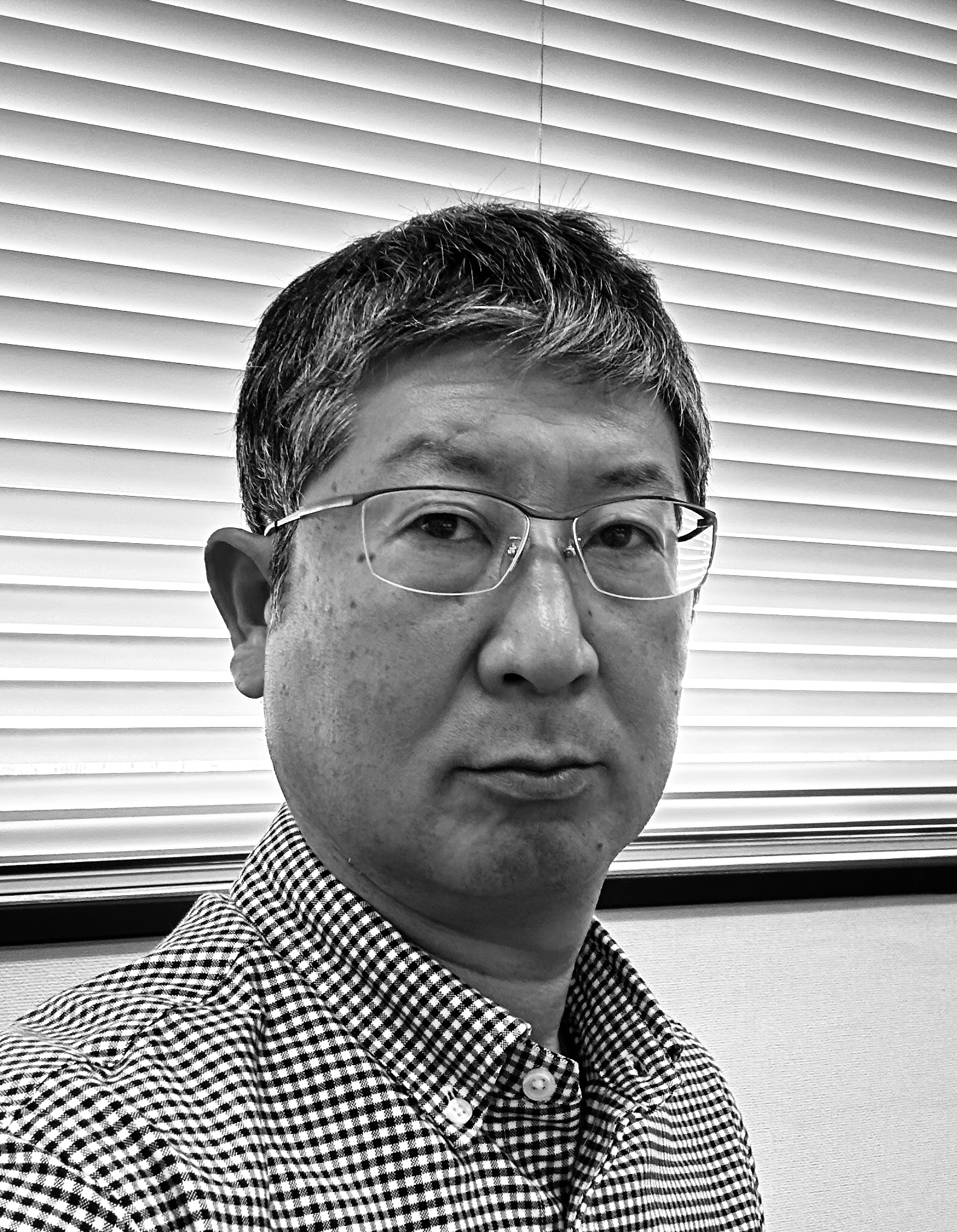
宮崎公立大学人文学部 教授(附属図書館長)
「情報伝達における利用品質」とは具体的にどのような概念ですか。また、教授が考える主な構成要素や評価指標について教えてください。
品質管理における重要な点は、顧客の要求を的確に把握して、これを科学的な品質規格、品質仕様として具体化し、この品質の製品を最も経済的に作り、市場へ投入し、顧客満足を得ることです。
この視点から、情報伝達における利用品質とは、情報の送り手から受け手に情報が伝わる際に、受け手が無理なく情報を理解できること、つまりユーザー指向の仕組みのことです。そこでは、顧客満足度が重要となります。
岡山市消防局を対象とした「災害対応ピクトグラム」に関する調査研究(2023年)では、どのようなデザインプロセスと評価手法を用いましたか。
岡山市消防局が製作した災害対応ピクトグラムは、NBC災害時において防護服などを着用した状態でのコミュニケーションを図るためのピクトグラムという、局地的なものです。
しかし、平成30年12月に岡山市で起きた、大規模ショッピングモールでの火災において、大規模な避難が実施され、その際にこの災害対応ピクトグラムが使用され、スムーズな避難に一役果たしました。
このことから、現在大きな課題となっている南海トラフ大地震への備えとして、ピクトグラムの活用が考えられます。
LMSにおけるユーザビリティ評価(2021年)の研究において、オンライン学習環境で明らかになった主な課題と、今後どのような改善アプローチが有効だとお考えかお聞かせください。
2020年に世界を襲ったCOVID-19パンデミックにより、私が勤務する大学においても完全なオンライン学習環境の構築が求められました。
それまでは、対面で行う授業の補助的に利用していたオンライン学習を、大学教育の前面に持って行く必要がありました。
その際、問題となったのがLMSのユーザビリティです。
LMSを活用していかに対面授業と同等の情報量を確保することと、その情報量を上手く処理できるような分かりやすく、使いやすいインタフェースの構築が必要だということが、この研究で分かりました。
「やさしい日本語」や訪日ムスリム旅行者対応に関する情報デザイン研究を踏まえ、異文化間コミュニケーションの現場で情報デザインを最適化するためのポイントは何だとお考えですか。
異文化間コミュニケーションというと英語の活用をイメージする人が多いのですが、日本に来ている外国人は、訪日ムスリム旅行者に代表されるような非英語文化圏の人の方が多いのが現状です。
言語によるコミュニケーションは非常に効率的ですが、上記のように英語や日本語だけでは、多様な国からの訪日が進んでいる状況において、問題が生じることが多いと思います。
そこで、情報デザインの手法であるインフォグラフィックスの活用がその解決策として有効と考えます。
著書『現代の品質管理』(1999年)を踏まえ、情報伝達の利用品質向上に向けた品質管理の手法を、情報デザインの領域に適用する際の課題と可能性についてご意見をお聞かせください。
品質管理で重要なことは、顧客満足を得ることです。
その点で、情報デザインにおいても同様な視点で考えることが重要です。情報デザインでは、このことをユーザー・センタード・デザインと言います。
もともと私は、品質管理を研究していましたが、研究を進めていく過程で情報デザインの領域を研究するようになりました。
その際のキーワードが「情報伝達の利用品質の向上」です。
情報デザインでは、科学的な手法が少ないような気がします。そのため、品質管理の手法を情報デザインに適用することの可能性を考えています。