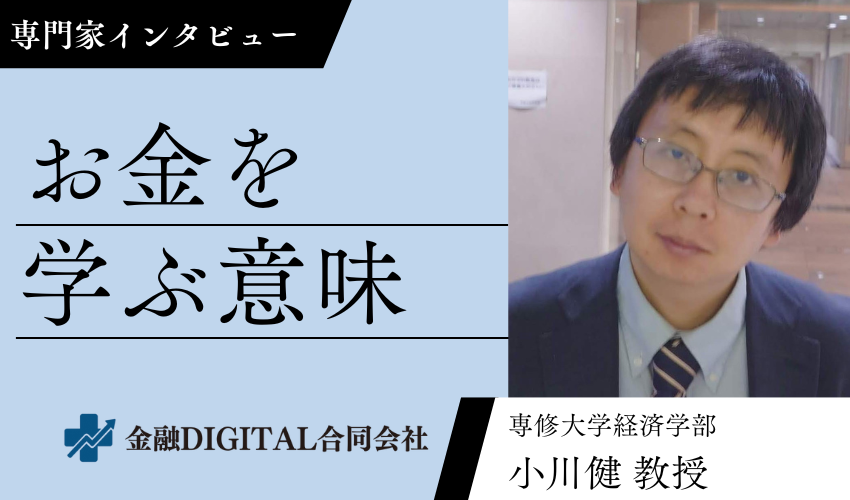専修大学経済学部 教授
するために-(日本経済教育学会第41回全国大会)(2025)
先生が今の研究分野を志したきっかけや理由を教えてください
私が暗号資産教育を自分の副専門(※1)にしようと思ったきっかけは、本来は専門ではない国際金融の分野を教える必要が出た段階で、何か引きを持たせられる話や独自の工夫が出来ないかと思ったことが始まりになります。外貨建て保険もそうですが、携わる事柄を教育に使えないかという意識はあります。
2015(平成27)年当時、一般の間ではビットコインを初めとする仮想通貨には、世界を変える可能性等での注目が集まっていました。当時はまだ法律整備も十分でなく(※2)、トラブルも一部報じられていた状況でした。
ただ、ビットコイン自体は下火になっても、そこで開発されたブロックチェーンを初めとする分散型台帳技術の仕組み自体は、将来どこかに組み入れられるとは当時でも言われていたので、知っておく意味はあったと言えるでしょう。
※1:元々の専門は近経貿易理論とそれを利用した水産物貿易です。
※2:2025[令和7]年現在、暗号資産は金融商品取引法での法規制が検討されていますが、日本で暗号資産の前身である仮想通貨の法整備が本格化されたのは、資金決済法で2017[平成29]年です。
資産運用では「長く続ける」「いくつかに分けて投資する」などの考え方がよく紹介されますが、なぜ大事なのでしょうか?
2つは性質こそ違いますが、共に「想定より悪い収益率」の悪影響を抑え、カバーする方法を増やすために大事です。リスク(振れ幅)の中で下振れの部分への対処ですね。
例えば、1つの会社の株だけに投資すると、その会社が倒産したら出資分は返ってきません。しかし、価値が上がるものと下がるものを共に持っていた場合、下がる分の悪影響を補えます。貴重なお金を資産運用するわけですから、悪く出ることが重ならないようにすることは大事です。
「落として全部一斉に割らないように、1つの籠に全ての卵を入れずに小分けにする」との有名な話には、その小分けにした卵の籠を同じ棚に全て乗せないように、という続きがあります。全部同じ棚に乗せると、その棚が壊れたときに全部一斉に割れるからです。共通の理由で悪くなることを防ぐために、いくつか下振れリスクが違うものに分けて投資するというわけです。
長く続けることも、下振れへのカバー手段の1つです。どこかの時期に損失が出ても、長く続けるなら残りの時間で損失分を補えます。また、一括して巨額は出せなくても長期ならその間に少しずつ出し続けることもできるからです。
教授ご自身も暗号資産や外貨の商品を持っていると聞きました。その経験をどのように学生や一般の人へ伝えていますか?
一般の人へ伝える部分は、各種HP記事等が中心になります。Facebookを利用したオンラインイベントを試してみたこともありますが、一般向けの話をいろいろ持っている方のほうが向きます。あとはNewsPicks等の「専門家と登録した人の知見を情報提供できる所」を利用しています。
学生に対しては講義内での説明が中心になりますが、科目を独自に作って教える以外にも、関連する内容が出て来る科目の一部に組み込んで教えることがあります。例えば、暗号資産や関連するステーブルコイン等の理解には、外国為替を扱う国際金融・国際経済の学部生向け枠組みが役に立つ部分があり、実際に私は国際経済の科目で暗号資産を単元の1つに取り入れています。
外貨の商品も同様の面があるのですが、邦貨(日本なら円貨)の商品に無い特徴のあるものは直接紹介しています。例えば、私は3大疾病になったら保険金が下りる米ドル建て保険にも入っています。この商品はかかった全額でなく一部に対し保険金が出る形にすると、為替リスクを被る代わりに保険金に対する平均的な保険料負担の比率を抑える形を取り、疾病時の負担の総額を抑える形が取れます。
これから投資を始める学生や社会人は、最初に何を学んだらよいと考えますか?
色々な意見はあると思いますが、私なら「複利とは何か」を最初に理解してもらうのが大事と答えます。長期・積立・分散等の概念や「ローリスク・ハイリターンは存在しない」点、更には金融所得税率等をはじめ、いろいろと早いうちに学ぶべき概念はあります。とはいえ、初めの段階では標語的な項目が多いので、学ぶにつれて吸収していけば良い部分があります。
一方で、複利の急激に増えていく感覚を捉えるには、直観に反して数学的な理解力を必要とする部分があり、数学に弱い人が最初に躓く危険性があります。細かな計算より、単利と違うこの増え方を最初に押さえておくのは大事でしょう。
よく「72の法則が使えれば無理して複利を理解しなくても」と捉える方がいますが、あの急激な増え方はまず感覚を持っておかないと、途中で置いていかれてしまいます。投資も借金も、複利での増え方を踏まえていないと、途中で止めてしまって勿体ない結果に繋がりえます。
ただし、これは普通の人の話。浪費癖が激しい人にはまず収支を把握し、収入の中から決めた範囲内で支出するところから学んだ方が良いでしょう。
最後に、これから資産形成やお金について勉強していく読者や学生へ、応援やアドバイスのメッセージをお願いします
お金は人生を豊かにも追い詰めることもできるだけに、その理解はあなたの人生と身を守る上で大事になります。資産形成には正解はありませんが、確実な間違いはある分野なだけに、既に知られている落とし穴に自分から嵌りに行くことのないように資産形成について学んでいく必要があります。
お金はあくまで人生の道具であり、あれば人生で取れる選択肢が増えるものです。本来は自分のお仕事や家族・友人、自分の時間を大事にできる範囲でお金について考えるべきです。時には無理をした収益性を狙わずに、単純なルールで他の時間を確保できるように、例えば現行NISAでも積み立て部分に使われることがある「ドルコスト平均法」は最善の方法でも最良の方法でもないのに、今でも使われています。
残りの使える時間が長いほど、複利での時間効果は大きいものがありますし、一時の損失もカバーしやすいです。一旦、自分の生活水準にかかるお金が大きくなると、そこから削るのは結構大変ということを意味する「ラチェット効果」を考えても、願わくば社会に出る前に、無理でも出来るだけ早くどこかで学んでおく意味はあるでしょう(知らないと騙される面もありますし)。