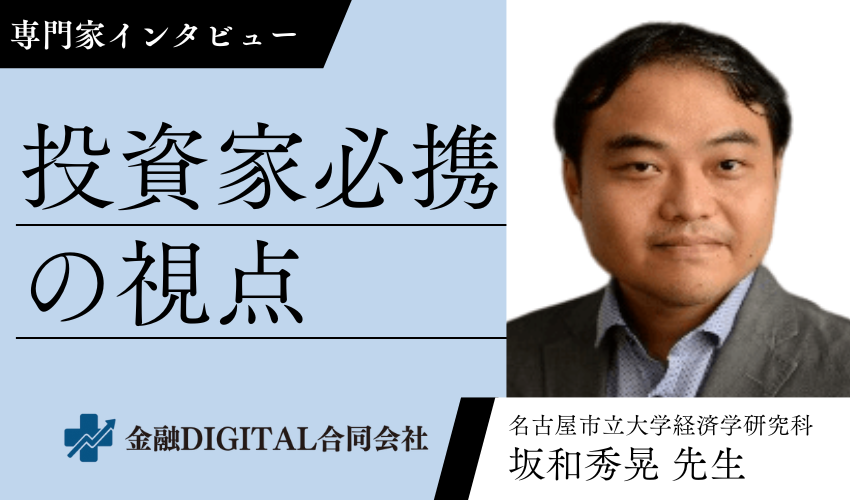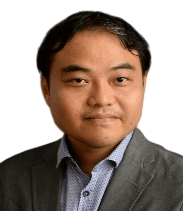
名古屋市立大学 経済学研究科 経営学専攻 准教授
コーポレートガバナンスやマーケット・マイクロストラクチャーについての分析・研究を始めようと思った理由やきっかけを教えてください
私がコーポレート・ガバナンスやマーケット・マイクロストラクチャーの研究を始めようと思った時期は、2000年代初頭の日本の会社(企業)や金融市場の制度的な変革が相次いだ頃です。それらの変化に興味を持ったのが、研究を始めようと思った大きなきっかけになります。
具体的に、企業を巡る改革としては、経営者に対するストック・オプション付与が1997年の商法改正で認められることで、経営者報酬の体系が変わりました。2003年の商法改正により「委員会等設置会社」が認められて、取締役会の中に、報酬委員会、指名委員会、監査委員会などを設置する企業などが増えました。
このように、企業のコーポレート・ガバナンスを大きく変容させる制度改正も多く、今後の日本企業のコーポレート・ガバナンスの変化に興味をもち、分析・研究を始めようと思うようになりました。
金融市場に関しては、2000年代からの東証での取引が完全システムによる自動取引に変更されるなどの大きな変化がありました。このような状況で「今後の金融市場での取引はどのように変わるか?」という点に興味を持ったことが、金融市場(マーケット)のミクロ構造を扱うマーケット・マイクロストラクチャーの分析・研究を始めようと思ったきっかけです。
個人投資家が長期投資スタンスを維持する上で、心がけるべきリスク管理のポイントは何だと思われますか?
個人投資家が長期投資スタンスを維持する上では、長期での利益実現を考慮することが重要です。その場合には「どのようなタイミングで自分の保有する(一部の)株式を手放すか?」という点が重要になります。
リスク管理のポイントとしては、
- 金融危機等による損失を回避する点
- 個別株式の低迷による損失を回避する点
の2点が重要になるかと思います。
1点目に関しては、2007〜2008年の世界金融危機のような大きな金融市場の変化により、日経平均株価指数が低迷するような局面が考えられます。このような場合は持株の保有を続けても、株価が下がり続ける可能性があります。
2点目に関しては、自身が投資する個別企業の業績低迷により、その企業の株主が保有する株式価値が下がり続ける場合が想定されます。決算報告で赤字が続く企業の場合などは、株主に対する配当を行うこともできないため、株主は配当による利益も期待できない状況になります。
特に、短期的な業績改善を見込める状況でない場合は、多くの株主がその株式を手放すことになり、株価が低迷することが予想できます。
したがって、リスク管理のポイントとしては、上記2点のような大きな損失が見込まれそうな場合に、早めに対象の持株を手放すことが重要になると思います。
高速取引・アルゴリズム取引の市場への影響について具体的に教えてください。
高速取引・アルゴリスム取引によって、短時間での市場での取引価格の変動が大きくなったことが知られています。金融市場では、株価の大きな変動は「バブル」として知られています。株価が急騰した後、その株価が暴落する「ポジティブ・バブル」とその崩壊といわれる現象が有名です。
学術的には、その逆で、株価が急落した後に再度上昇する「ネガティブ・バブル」とその崩壊といわれる現象が知られています。
高速取引・アルゴリズム取引の導入によって、これらのバブルとその崩壊のような大きな価格変動が、1日の取引の中の数分間といった短い時間で起こるようになりました。このような現象は、フラッシュ・クラッシュと呼ばれています。2010年5月6日に米国で起こったフラッシュ・クラッシュでは、ダウ平均(ダウ工業株30種平均指数)が、5分あまりで573ドルも急落し、前日終値から1000ドル弱急落したことが知られています。
経済学や金融分野の専門家を志す学生が大学・大学院で身に付けておくべき基礎スキルや知識を教えてください。
経済学や金融分野の専門家を志す場合、まずは基礎的な理論モデルを学ぶ必要があります。特に、ミクロ経済学の学修が必要になります。
現在の学問の世界では、データ分析の比重が高まっていることに注意が必要だと思います。10~20年前の状況では、経済理論のモデル分析が中心でしたが、データの利用可能性が高まるとともに「理論モデルで得られた結論は、本当に社会経済や金融のさまざまな現象を説明できるか?」といった点に注目が集まるようになりました。
理系の分野で、アイザック・ニュートンの理論である「万有重力の法則」も、後の科学者の実験により検証が進められたように、経済学や金融の分野でも多様なデータの利用可能性が高まるとともに、データ分析で理論モデルが検証されるようになっています。
したがって、基礎スキルとして、理論の学習のみならず、データ分析を行うための手法を身につけるための「統計学」「計量経済学」などの学修が重要になっています。
最後に、金融業界に携わりたいと考えている読者にメッセージをください。
金融業界は、変化の激しい業界です。我が国においては「貯蓄から投資へ」をスローガンに金融市場の改革が進むとともに、投資に携わる投資家も増えて、その規模も拡大しています。
証券を扱う直接金融の世界では、金融市場を巡る取引の現場も20年余りで大きく変容しています。2000年代以降の我が国において、株式の注文システムの自動化、証券手数料の自由化などで、ネット証券での売買なども可能になり、個人投資家の売買も増えていく時代になりました。
また、直接金融の業界で扱われる金融商品の種類も増えています。このような変化に伴い、金融商品を発行する企業側なども、さまざまな金融商品を発行して、企業の財務活動を考える必要が出てきます。
したがって、投資家に対するサービス、あるいは企業に対するサービスを提供する金融業界の人材のニーズは高いと思います。是非とも、関心のある読者の皆様は、このような今後のニーズの高いと思われる金融業界の変遷に興味を持っていただければと思います。