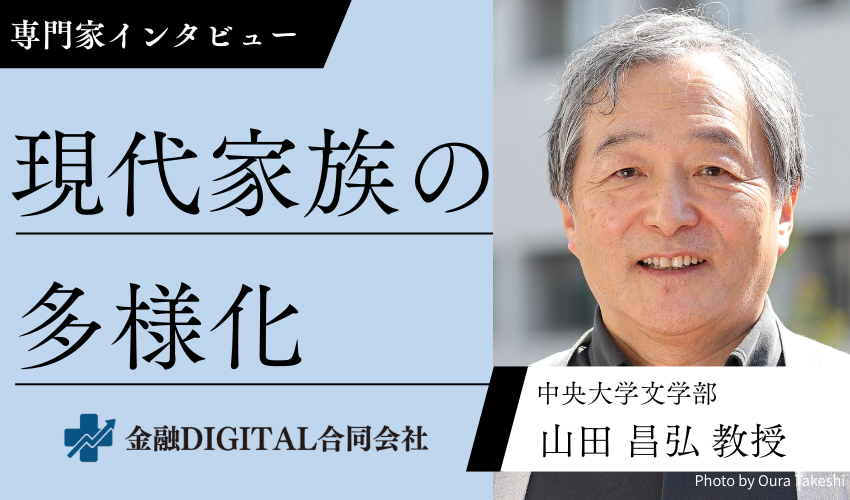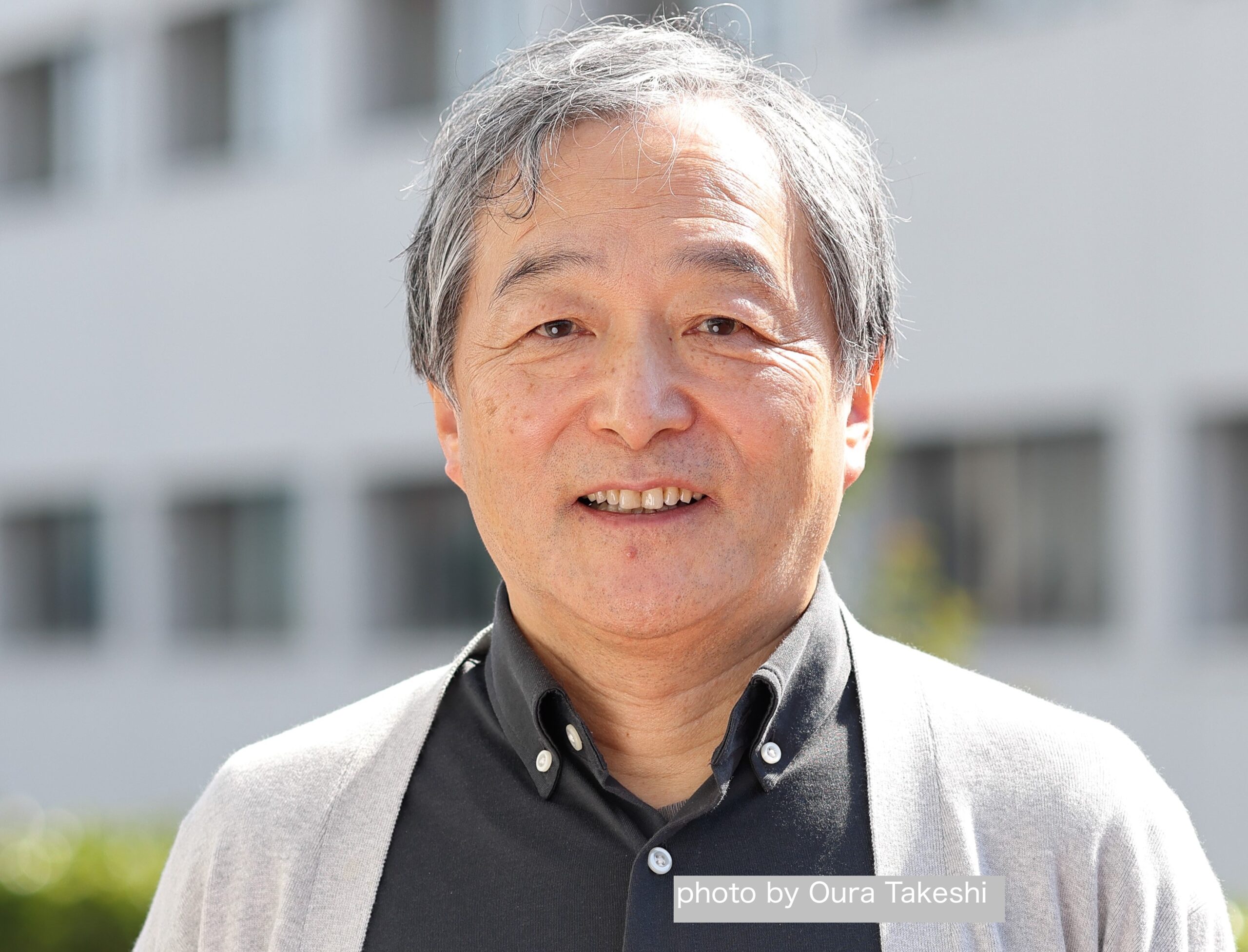
中央大学文学部 教授
1986年同大学院社会学研究科博士課程退学後、東京学芸大学教授を経て、2008年より中央大学文学部教授。
教授の「パラサイト・シングル」という概念に関して、現在の20〜30代において、自立支援に必要とされる政策的アプローチは何だとお考えでしょうか。
離家、親から離れて住むことを推進する政策くらいしか思いつきません。
日本では、結婚までは親と同居した方がよいという文化が強く、文化を変えることはなかなか難しい。
さらに、経済的に親と同居した方が合理的です。一人暮らしの若者に住宅支援をしたり、シェアハウスの整備を進めたりすることなどが考えられます。
一人暮らしが増えれば、結婚も増えるかもしれません。
若年層の将来不安や格差の固定化を表す「希望格差社会」という概念は、コロナ禍や物価高を踏まえた現代では、どのような変容を遂げていると分析されていますか。
2004年出版の『希望格差社会』では、将来豊かな生活を保てると考える若者と、将来豊かな生活になれないから結婚を先送りするという若者の間の格差でした。
新型コロナ後には、若者が歳をとり、格差が中年まで広がり、40代で未婚かつ低収入の人が増えています。
特に親同居の彼らが老後不安を抱くようになっているのが今の状況です。
また、若い人の親の格差が広がった結果、親ガチャというように、親の経済力が低い人は、将来、結婚して豊かな生活はできないとあきらめる人も出てきています。
婚活市場のデジタル化やマッチングアプリの普及が進む中で、恋愛・結婚の社会的意味づけの変容や、若者が抱える葛藤をどう分析されていますか。
結婚サービス業の興隆やマッチングアプリの普及は、「結婚市場」を作り出すことにより、沢山の人と出会えるという状況を作りました。
結婚にはお金(より安定した経済環境)が必要と考える傾向が強い日本では、婚活強者と婚活弱者に分かれている傾向を助長します。収入が比較的高い男性には相手がすぐに見つかりますが、そうでない男性にとってはますます見つかりにくい傾向が強まります。
女性にとって、もっといい人と出会えるかもしれないという期待を抱かせるからです。そのため、恋愛がますます衰退する一因と考えます。
現在の「多様な家族」像(未婚、非婚、事実婚、シングル世帯等)の増加をどのように評価されていますか。
今の40代以下は、結婚確率75%以下、離婚確率25%以上になると推計されています。つまり「標準的家族(結婚して離婚せず)」で過ごせる人は、50%以下ということです。
それに、専業主婦であることを加えれば、10%にしかなりません。つまり、今の社会保障制度は、この10%を対象に作られているのです。
年金制度などは個人勘定を徹底して、独身でも離婚しても再婚しても不利にならないような仕組みが求められます。
ジェンダー平等の進展と共に、育児や介護といったケア責任の分担も見直されつつあります。教授はこのような家族内役割の再編をどのように捉えておられますか。
ジェンダー平等がこのまま進めば、男女が公平に仕事と育児家事を分担する家族が増えるでしょう。もちろん、各夫婦の事情により分担割合は違うとは思います。
専業主婦は一部の高収入の夫のみに可能な家族形態となります。男性も将来よい生活を築くには、妻の収入も必要と考え、育児を負担しても共働きを望む若者が増えています。
逆に、専業主婦になりたい女性は結婚しにくくなります。専業主婦で豊かな生活を築けるような高収入男性の数が激減しているからです。